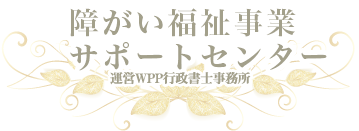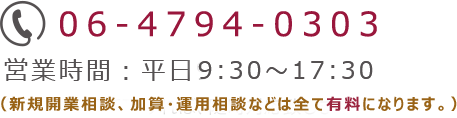箕面市、池田市、茨木市、摂津市での放課後…
放課後等デイサービス、児童発達支援の「実地指導」が不安な方へ

放課後等デイサービス、児童発達支援の実地指導
この記事をご覧になられているということは、「実地指導の通知が来た!」「実地指導が不安だ!」「実地指導にむけて書類をしっかり整備したい!」という方ではないでしょうか。
もし、実地指導関係で、当事務所にご依頼したいとお考えの場合は、電話か専用フォームでお問い合わせをいただければと思います。
弊所は障がい福祉事業に専門特化しており、平成26年創業で10年の実地指導のサポート歴があります。
コロナ禍での実地指導が停止している場合を除き、これまで、通算150以上の実地指導のサポートを行っています(令和4年度22件件、令和5年度27件の実地指導サポートしており、すべてについて当日立会いを行っています)。
留意事項としまして、
- 基本的に本HPは厚労省の発出する資料と大阪府下の解釈などよって構成されておりますが、指定権者(行政)で解釈が異なる場合がありますので、必ず、指定権者に確認をお願いいたします。
- 内容についての無料相談は一切お受けしておりません。
放課後等デイサービス、児童発達支援とは
放課後等デイサービス(放デイ)
主に6歳から18歳(就学年齢)の障がい児が、学校の放課後や夏休みなどの長期休暇に訓練や社会との交流促進等を提供することで、障がい児の自立を促進させ、放課後等の居場所づくりを行います。
児童発達支援(児発)
未就学(小学生以上は放課後等デイサービス(高校等への進学を行っていない場合は、18歳誕生日まで児童発達支援が可能 大阪市))で障がいのある児童に対して、日常生活における基本的動作指導、コミュニケーションや集団生活への適応のための訓練を行います。
障がい福祉事業全般における実地指導の必要書類とポイント
(1)人員に関するポイント
| 必要書類 | ポイント |
| ①勤務体制の一覧表、シフト表 |
|
| ②前年度平均利用者数を調べたもの |
|
| ③出勤簿(タイムカード) |
|
| ④給料明細(控え) |
|
| ⑤雇用契約書(労働条件通知書) |
|
| ⑥研修修了証、資格証 |
|
| ⑦秘密保持の誓約書 |
|
| ⑧雇用保険 | |
| ⑨健康診断の記録 |
|
| ⑩研修計画と記録 |
|
(2)サービス提供に関するポイント
| 必要書類 | ポイント |
| ①重要事項説明書 |
|
| ②利用契約書 |
|
| ③個人情報同意書 |
|
| ④アセスメント |
|
| ⑤個別支援計画原案 | |
| ⑥個別支援計画の担当者会議事録 | |
| ⑦個別支援計画 |
|
| ⑧モニタリング |
|
| ⑨契約内容報告書 |
|
(3)運営に関するポイント
| 必要書類 | ポイント |
| ①運営規程 |
|
| ②送迎記録 |
|
| ③自己評価に関する記録 | |
| ④事故発生報告書、ヒヤリハット報告書 | |
| ⑤苦情相談の記録 | |
| ⑥虐待防止委員会の設置、開催の議事録、指針など |
|
| ⑦身体拘束適正化委員会の設置、開催議事録、指針など |
|
| ⑧BCP(災害と感染症)関係、感染対策委員会の設置など |
|
| ⑨点呼表 |
(4)請求に関するポイント
| 必要書類 | ポイント |
| ①法定代理受領通知 |
|
| ②利用者への請求書、領収書 |
|
| ③実績記録表 |
|
(5)整備すべきマニュアル
| 感染症防止マニュアル |
| 事故防止マニュアル |
| 虐待防止マニュアル |
| 緊急対応マニュアル |
| 非常災害マニュアル |
| 身体拘束関連マニュアル |
(6)その他に関するポイント
| 必要書類 | ポイント |
| ①賠償責任保険の証書 |
|
| ②会計書類 |
|
| ③非常災害訓練、火災訓練の記録 |
|
放課後等デイサービス、児童発達支援の実地指導とは
放課後等デイサービス、児童発達支援の実地指導で指摘される 過誤が発生しやすい 代表的な部分を記載しました。
(1)人員配置について
- 放課後等デイサービス・児童発達支援の基準配置が資格者(保育士や児童指導員など)でなければならないため、勤務体制
- 各加算における人員配置(児童指導員加配や専門的支援加算など)
がチェックされることになります。
加算を取得している場合
下記加算を取得している場合は、人員配置基準に上乗せや別途要件が必要になります。
①児童指導員加配体制加算、専門的支援加算を算定している場合
②福祉専門職員等配置加算を算定している場合
③強度行動障害児支援加算を算定している場合
④特別支援加算を算定している場合
医療的ケア区分を算定している場合
看護師を配置し医療的ケアを行った場合に算定されます。
医療的ケア区分は行政への届出がなくとも、請求システム上算定されることから誤って請求をするケースもあるので要注意です。
減算をしなければならない場合
①児童発達支援管理責任者や保育士・児童指導員等が欠如している場合
- 最低人員基準を1割を超えて欠如した場合 は、翌月から減算
- 最低人員基準を1割の範囲で欠如した場合 は、翌々月から人員欠如が解消するまでの間、減算
②定員超過減算
定員を一定割合で超過した場合に減算になります。
(2)個別支援計画の作成について
放課後等デイサービス、児童発達支援を含む障がい福祉事業は、利用者毎に個別支援計画を作成する必要があります。
また、放課後等デイサービス、児童発達支援は 6か月に一度モニタリング を行うことが義務付けられており、個別支援計画が未作成であ
れば減算となります(詳しくは個別支援計画の記事を参照してください。)。
(3)送迎加算
送迎加算は、原則利用者宅や学校から事業所へ送迎した場合の加算で、送迎記録などを作成し、送迎時間や誰が誰を送迎したかなどの記録を残すことが重要です。
基準配置の1人目の資格者は送迎にでることは不可ですし、 基準配置の2人目は誰か別の資格者で穴埋めする必要があります。
徒歩送迎などは加算対象外となります。
一定の要件を満たす場合
放課後等デイサービス、児童発達支援で、医療的ケア区分に応じた算定をしている事業所で、喀痰吸引等が必要な利用者で看護師を伴い送迎している場合については、送迎加算に上乗せ加算(+37単位)を算定できます。
(4)延長支援加算
運営規程にある営業時間が8時間以上ある場合に取得できる加算ですが、延長時間帯に直接支援業務として従事する職員を1名以上配置する必要があります。
個別支援計画の位置づけも必要です。
(5)注意すべき加算
ここでは届出が不要な加算を記載しますが、これらはいずれも記録などが必要になりますので注意が必要です。
取得している事業所さんが多い加算です。記録がない事業所も散見されます。
④医療連携体制加算
主治医の指示書や看護師の記録を備え付けて下さい。
6 その他減算をしなければいけない場合
自己評価結果等未公開減算
1年に一回以上自己評価と保護者の評価結果を公表していない場合(行政への届出をしていない場合)に15%減算。
Q ホームページでの情報の提供が必要になりましたが、どうのようなものですか?
A 省令改正によりガイドラインに沿って、自己評価の結果をインターネットを通じて公表することが義務付けられました。
具体的には、
1. 利用する障がい児とその保護者の意向、障がい児の適性、障がいの特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制整備状況
2. 従業者の勤務体制、資質向上のための取組状況
3. 放課後等デイサービス事業用の設備、備品等の状況
4. 関係機関と地域との連携、交流等の取組状況
5. 利用する障がい児とその保護者に対する必要な情報提供、助言その他の援助の実施状況
6. 緊急時等における対応方法と非常災害対策
7. サービス提供に係る業務改善のための措置の実施状況
7 その他
過誤とは直接関係ありませんが、運営基準をしっかり確認することが重要です。
- 重要事項説明書と運営規程の整合性
- 従業員に対して健康診断を受けさせているか
- 個人情報の秘密保持の誓約書を従業員からとっているか
- 事故発生、虐待防止、緊急避難、感染症対応、相談苦情、身体拘束適正化などのマニュアルを整備しているか
- おやつ代などの実費請求について、事業所側で利益となる部分については利用者に返還を支持されることもある
など
8 加算関係の記録
・加算については記録をしっかり残しておく必要があるものについて、記録していますか?
送迎記録、欠席対応加算、事業所内相談支援加算、家庭連携加算、医療連携体制加算など
基本的な項目は、他の障がい福祉サービスの実地指導と同じですが、当然ながら、書面でのチェックになりますので、日ごろから管理者・児童発達支援責任者が中心になって書類作成を行っていく、または書類作成の指示を出していくことが大切です。
実地指導対策・書類点検サービス(模擬実地指導)・短期集中コンサル
こんな障がい福祉事業所が対象です
- ①実地指導・監査が不安だ
- ②書類が揃っているか不安だ
- ③書類の記載方法などが不安だ
- ④人員配置が整っているか不安だ
- ⑤既に実地指導を受けたが、行政側の話が良く分からない
- ⑥その他、漠然と不安だ
これらに1つでも当てはまりましたら、一度ご検討下さい。
当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。
申し訳ありません。無料相談は行っておりません。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。