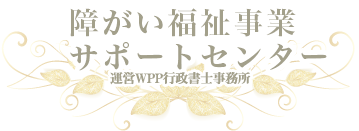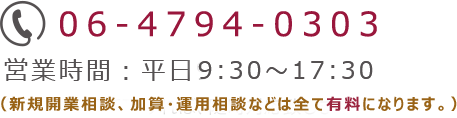生活介護(障がい)の時間減算をわかりやす…
就労継続支援の「施設外就労」と「施設外支援」の比較

就労継続支援A型・B型・就労移行には、事業所の外で就労を行う「施設外就労」と「施設外支援」が存在します。
混同される方が多いので、今回は施設外就労と施設外支援の違いについて、説明していきます。
→ 就労継続支援A型
→ 就労継続支援B型
施設外就労
事業所外の企業や官公庁などで作業を行うような働き方を施設外就労といい報酬算定の対象となる要件として下記となります(施設外就労加算は令和3年報酬改定で廃止されました)。
また利用者も多様な働き方ができるということでメリットがあります。
① 施設外就労に出る利用者は、定員と同数であること
- 例えば、定員が20名の事業所である場合、1日の施設外就労を行う利用者は20名となります。
② 配置基準の厳守(7.5:1 or 10:1)
- 常勤換算方式により配置
③ 請負契約を締結すること
- 同一法人での契約はできません
- 施設外就労先から機械等を借りる場合、賃貸借契約書や使用貸借契約書を締結すること
④ 利用者は、施設外就労先の従業員からではなく、職業指導員を介して指示を受けること
⑤ 月に2回、訓練目標に対する評価を受けること
➡ 令和3年度報酬改定で削除。評価頻度については指定権者に確認すること
⑥ 運営規程に位置付けられていること
⑦ 個別支援計画に位置づけされていること
⑧ 緊急時の対応ができること
⑨ 施設外就労報告書を毎月1回提出すること(指定権者である市役所等)
施設外支援
施設外支援は、施設外就労と同じように報酬対象とすることができますが、加算の対象となりません。
① 利用者または事業受入事業者から状況の聞取りと日報の作成
② 運営規程に位置付けられていること
③ 個別支援計画が事前に作成され、施設外支援内容について1週間ごとに必要な見直しが行われていること
④ 緊急時の対応ができること
⑤ 支援期間は180日以内
支援先は
- 一般企業での実習
- 他の就労継続A型で実習
- 委託訓練先での実習
- 在宅就労の場合
- トライアル雇用
施設外支援の注意点
施設外支援と事業所での利用を同日でおこなった場合は施設外支援として取り扱います。
施設外就労と施設外支援の比較
上記について表にして比較してみました。
|
|
施設外就労 |
施設外支援 |
|
支援を行う職員 |
要(7.5:1 or 10:1) |
否 |
|
請負契約 |
要 |
否 |
|
報酬算定の対象となる支援の要件 |
配置基準の厳守
実績記録表への記載 |
利用者または事業受入事業者から状況の聞取りと日報の作成
事前に支援の内容について個別支援計画に位置づけされ、施設外支援内容について1週間ごとに必要な見直しが行われていること (支援により就労能力や工賃・賃金の向上、一般就労への移行が認められること) 緊急時の対応ができること
実績記録表へ記載 |
| 個別支援計画の位置づけ | 要 | 要
施設外支援内容について1週間ごとに必要な見直しが行われている必要がある |
|
緊急時の対応 |
要 |
要 |
|
運営規程の記載 |
要 |
要 |
|
提供期間 |
無 |
毎年4月1日から翌年3月31日のうち180日 |
|
その他
|
施設外就労者と同数の数を、事業所に新たに受入れ可能
|
利用者へは交通費や日当 契約書までは不要であるが書面で行うべき。この場合、日当や交通費程度の支払いでもよい。OJTだから |
※施設外実習という考えの行政もあります。
トライアル雇用
トライアル雇用については施設外支援の要件を満たしている場合、基本報酬は算定可能となります(就労継続支援A型の利用者はトライアル雇用不可)。
事前に支援の内容について個別支援計画を3カ月毎に作成し(施設外サービス提供時は1週間毎)、かつ見直し行うをことで、就労能力や工賃・賃金の向上、トライアル雇用終了後に一般就労との移行に資すると認められること)
施設外支援のトライアル雇用時の個別支援計画計画の留意点
計画の作成と見直し時
- 事業所、本人及び関係者が参加の上、協議を行い、必要に応じてハローワークや受入れ企業から意見聴取を行う。
計画の見直し時
- 延長の必要性や実施内容の見直し等を協議する。
よくある質問
Q 定員10名の事業所では、施設外就労を何名出すことができますか?
- A 施設外就労は10名となります。
まとめ
施設外就労と施設外支援は、文字が似ていますが、似て非なるものです。
経営の安定や就労の多様化、施設外就労者と同数を新たに受入れるという実質的な定員増加という側面からも積極的に施設外就労先を見つけることが重要です。
当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。
申し訳ありません。現在無料相談は行っておりません。
コンサルメニュー
書類点検メニュー
実地指導直前対応
〇顧問行政書士等に不満・不信感等がある方は、セカンドオピニオンサービスをご覧ください。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。