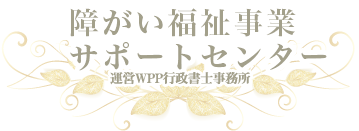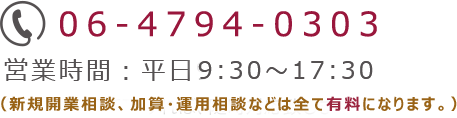生活介護(障がい)の時間減算をわかりやす…
医療連携等体制加算について分かりやすく解説

医療連携体制加算
文字どおり医療機関等と連携することで、看護職員が障がい福祉事業所を訪問して利用者に対して、看護をおこなった場合や介護職員等にたん吸引等の指導をおこなった場合に加算されるものです。
要件
1 医療機関等と委託契約等をおこない看護師が訪問し看護を行う(看護師の直接雇用も可能)。
2 原則、主治医の指示書が必要であり、定期的に提供状況の報告を行う必要もあります。
3 個別支援計画の位置づけが必要
※ 和歌山市HP「医療連携体制加算の算定に係る要件の取り扱いについて」
該当サービス
就労継続支援A型、B型、就労移行支援、共同生活援助(グループホーム)、放課後等デイサービス、児童発達支援、短期入所 など
加算区分(1) 就労系、共同生活援助の場合(Ⅶ)のみ共同生活援助独自のもの)
| 区 分 | 要 件 | 単 位 | |||
|
医療連携体制加算(Ⅰ) |
看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して1時間未満の看護の提供を行った場合(非医ケア) |
32単位/日 |
|||
|
医療連携体制加算(Ⅱ) |
看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して1時間~2時間未満の看護の提供を行った場合(非医ケア) |
63単位/日 |
|||
|
医療連携体制加算(Ⅲ) |
看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して2時間以上の看護の提供を行った場合(非医ケア) |
125単位/日 |
|||
|
医療連携体制加算(Ⅳ) |
看護職員が事業所を訪問してい医療的ケアを必要とする利用者に対して看護の提供を行った場合
|
|
|||
| 医療連携体制加算(Ⅴ) | 看護職員が看護職員に喀痰吸引等の指導のみを行った場合 | 500単位/日 | |||
| 医療連携体制加算(Ⅵ) | 研修を受けた看護職員等が喀痰吸引等を実施した場合 | 100単位/日 | |||
|
医療連携体制加算(Ⅶ) (GH、短期入所のみ) |
看護師を1名以上配置する等、日常的な健康管理、医療ニーズが必要な場合に適切な対応がとれる体制を整備している場合
・看護師は管理者、サビ管、生活支援員、世話人の兼務でも可能。(専従が必要) ・看護師の配置が必要(准看護師は不可)
・Ⅰ~Ⅵの併用可 ・他の事業所との兼務が可能(非常勤短時間で可能) ・利用者に対する日常的な健康管理 ・通常時、体調悪化時における医療機関(主治医)との連絡調整 ・24時間連絡体制の確保 ・「重度化した場合における対応に係る指針」の作成が必要 ・訪問看護ステーション等との連携も可能 |
39単位/日 |
看護職員とは?・・・看護師、準看護師、保健師となります。
※「重度化した場合における対応に係る指針」・・①急性期における医師や医療機関との連携体制、②入院期間中におけるGHにおける家賃や食材料費の取り扱いなどを盛り込む。
よくある質問(医療連携体制加算(Ⅶ))

Q 医療連携体制加算(Ⅶ)の算定要件で看護師の基準時間は設定されていますか?また24時間音コールでも可能ですか?
- A 時間設定はありませんが、「利用者に対する日常的な健康管理」「通常時、体調悪化時における医療機関との連絡調整」等が必要なことからこれらを行う必要な時間の確保が必要です。勤務実態がないオンコール体制では算定は不可となります。
Q 提携している医療機関の医師が定期的に診察する場合や訪問する看護師で医療連携体制加算(Ⅶ)の算定要件は可能ですか?
- A 看護師確保をせず、単に提携医師による定期診断だけでは算定不可となります。
Q 医療連携体制加算(Ⅶ)で看護師が他の事業所の看護師を活用する場合、この看護師が夜勤を行うときもグループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよいですか?
- A 他の事業所の看護師を活用する場合、他事業所で夜勤をしている看護師がグルホからの連絡を受けて必要な措置(医療的対応について相談できる体制)をとることができる体制となっていれば、確保となります。
Q 「重度化した場合における対応に係る指針」はどう周知すればよいですか?
- A 重説に盛込むか重説に補足書類として添付し、入居の際に説明することが望ましいです
加算区分(2)放課後等デイサービス、児童発達支援の場合
| 区 分 | 要 件 | 単 位 | |||
|
医療連携体制加算(Ⅰ) |
看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して1時間未満の看護の提供を行った場合(非医ケア) |
32単位/日 |
|||
|
医療連携体制加算(Ⅱ) |
看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して1時間~2時間未満の看護の提供を行った場合(非医ケア) |
63単位/日 |
|||
|
医療連携体制加算(Ⅲ) |
看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して2時間以上の看護の提供を行った場合(非医ケア) |
125単位/日 |
|||
|
医療連携体制加算(Ⅳ) |
看護職員が事業所を訪問してい医療的ケアを必要とする利用者に対して4時間未満の看護の提供を行った場合 |
|
|||
| 医療連携体制加算(Ⅴ) | 看護職員が事業所を訪問してい医療的ケアを必要とする利用者に対して4時間以上看護の提供を行った場合 |
|
|||
| 医療連携体制加算(Ⅵ) | 看護職員が看護職員に喀痰吸引等の指導のみを行った場合 | 500単位/日 | |||
| 医療連携体制加算(Ⅶ) | 研修を受けた看護職員等が喀痰吸引等を実施した場合 | 100単位/日 |
※ 看護職員とは?・・・看護師、準看護師、保健師となります。
※ 1日3人以上の医療的ケア児を看護する場合は医療連携体制加算は算定できず、 医療的ケア区分 で算定する必要がある。
注意点

医療連携体制加算は、医療機関との契約に基づく必要があることから、看護師等を訪問させる場合は、医療機関と委託契約を締結する必要があります。また、雇用するような場合は、主治医等の指示書(個別)が必要となります。
①事業所で1枚の指示書で加算算定している場合、実地指導により過誤請求処理となります、ご注意下さい。
②医師の指示に基づかない看護の提供は加算対象外ですし、有効期間は6か月です。
③看護行為等を個別支援計画に明確に記載する必要がありますし、実施記録も必要です。
→ 訪問看護ステーション等と契約をしている場合は、必ず看護の記録を事業所で保管して下さい。
④看護師一人で看護可能な利用者数は8人まで。
医療行為に当たらない行為
「医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について」(H17.7.26 医政第 0726005 号厚生労働省医政局長通知)に掲げている行為に関しては医療行為でないとされ、医療連携体制加算の行為には該当しません。
⇒ 例:体温測定、血圧測定、軽度な傷等の処置、体調が良好な利用者に対する服薬指導(既に処方等が終了し、服薬に医学的な配慮が必要でない場合)等)
訪問看護ステーションなど障がい福祉事業以外の事業所からの「医療連携体制加算」のご相談はお受けしておりません。
当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。
申し訳ありません。現在無料相談は行っておりません。
コンサルメニュー
書類点検メニュー
実地指導直前対応
顧問行政書士等に不満・不信感等がある方は、セカンドオピニオンサービスをご覧ください。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。