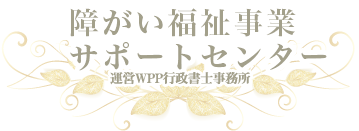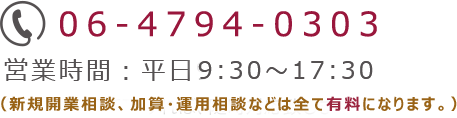日中系サービスの初期加算とは? 新規利用…
就労継続支援A型の「利用者を雇用する」ために知るべき3つのポイント

就労継続支援A型は、障がい福祉サービスで唯一利用者を雇用するサービスのため、利用者との雇用関係の書類作成する必要や労働法規を遵守する必要があります。
「利用者を雇用する」こと
就労継続支援A型で、忘れてはいけないことは、「利用者は雇用者でもある」ということです。ということは、従業員のカテゴリーは、「従業員」「利用者であり従業員」の2パターンに大別されます。
1 必要書類(利用者)
通常の障がい福祉サービスでは、利用者との雇用関連の書類は必要ありませんが、就労継続支援A型については、利用者と雇用契約を締結するということですので、
- 労働条件通知書(雇用契約書)
- 就業規則
の書類作成が法令上必要になりますし、雇用保険の加入も必要となります。
また場合によっては、36協定の締結や社会保険の加入義務が出てくる場合もあります。
2 賃 金
就労継続支援A型は、利用者に対して、各都道府県に定められる最低賃金以上を原則支払う必要があります。
3 労働時間と利用時間

利用者を雇用するということは、労働法の適用を受けるということですので、週20時間以上の労働者は雇用保険の加入が必要になります。
令和3年度の報酬改定により「1日の平均労働時間方式」から総合評価をもって実績(指定後の次年度から評価)とする「スコア方式」が導入されました。
スコア方式(下記5項目)
| 評 価 | 判定スコア | |
| 労働時間 | 1日の平均労働時間により評価 | 5点~80点で評価 |
| 生産活動 | 前年度及び前前年度における生産活動収支により評価 | 5点~40点で評価 |
| 多様な働き方 | 利用者が多様な働き方を実現できる制度の整備状況と実績により評価 | 0点~35点で評価 |
| 支援力向上 | 職員の支援力向上の取組実績により評価 | 0点~35点で評価 |
| 地域連携活動 | 地元企業と連携した高付加価値商品開発、施設外就労による働く場の確保などの連携した取組実績により評価 | 0点~10点で評価 |
労働時間
1日の平均労働時間が長いほど賃金がかかることから、労働時間が長いほど評価されるます。
労働時間=労働時間の合計数÷利用者の合計数
| 1日の平均労働時間 | 点数 |
| 7時間以上 | 80点 |
| 6時間以上7時間未満 | 70点 |
| 5時間以上6時間未満 | 55点 |
| 4時間30分以上5時間未満 | 45点 |
| 4時間以上4時間30分未満 |
40点 |
| 3時間以上4時間未満 | 30点 |
| 2時間以上3時間未満 | 20点 |
| 2時間未満 | 5点 |
※賃金が発生しない時間については労働時間に算入しない
①面談の時間は実際に労働しておらず、賃金が発生していないので算入しない。しかし労働扱いで賃金は発生していれば労働時間に算入。
②有給取得は賃金が発生しているので労働時間に算入。
③予見できない理由で短時間労働(1日の労働時間が4時間未満)になった場合、短時間労働となった日から90日を限度として、延べ労働時間・延べ利用者から除外することができる
予見できない理由
- ア 進行性の難病
- イ 利用開始時に病院に入院し退院直後に短時間労働となった場合
- ウ 家族の介護を受けて利用していたが、家族の病気などで居宅介護等のサービスが必要のになった場合
- エ 精神障がいなどで利用開始時には予期できない体調不良があり短時間労働となった場合
よくある質問

Q 利用者の副業やアルバイトは認められますか?
- A 認められません。就労系サービスは一般就労が困難な方を対象としていることから、副業やアルバイトができる場合は、就労系サービスを受けることになじまないからです。また、副業やアルバイトを行っていた利用者のこれまでの算定分について過誤請求(返金)を求める行政もあります。
Q 利用時間内で、研修を行った場合、時給を支払う必要はありますか?
- A 業務命令としての研修である場合は支払う必要があります。
当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。
〇 書類点検サービス(模擬実地指導)を希望の方はこちらをご覧ください。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。