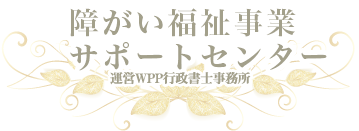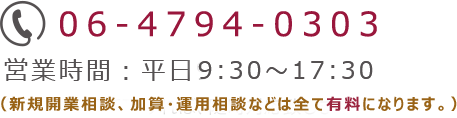共同生活援助(グループホー…
【人員配置基準】共同生活援助(グループホーム)
共同生活援助(グループホーム)の人員配置基準
共同生活援助(グループホーム)の許可(指定)の手続きには、どんな人を何人配置する必要があるのでしょうか?
どんな人が必要か?
人員配置基準
| 職種 | 配置数 | 常勤要件 | 備考 |
| 管理者 | 1名以上 | あり | |
| サービス管理責任者 | 1名以上 | なし | 利用者数 31 人以上:1人に、利用者数が 31 人を超えて30 又は その端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 |
| 生活支援員 | 1名以上 | なし | 常勤換算で、次の①から④までに掲げる数の合計以上
① 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数 ② 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数 ③ 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数 ④ 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数 |
| 世話人 | 1名以上 | なし | 6;1(基本単位) |
※管理者とサビ管の兼務が可能です。
管 理 者
管理者とは、職員の管理、利用者の申込みに係る調整、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行うことが主な仕事であり、簡単に説明すると、事業所を統括することが管理者の仕事ということになります。
資格要件はありません。
サービス管理責任者
サービス管理責任者(通称「サビ管」)とは、障がい福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者を言います。
具体的には、利用者のアセスメントの実施、個別支援計画の策定・評価、サービス提供のプロセス全体を管理します。
「事業所を統括する管理者」と「利用者とサービス提供を管理するサービス管理責任者」と区分けすると分かりやすいです。
次にサービス管理責任者の要件を確認していきます。
サービス管理責任者の要件となる実務経験年数
| A 実務経験 | B 研修受講要件 | |||
| 相談支援業務 | 直接支援業務 | |||
| ①資格なし | 5年かつ900日 | 10年かつ1800日 | ・相談支援初任者研修(2日以上) &
・サービス管理責任者研修 |
|
| ②有資格者 | 社会福祉主事任用資格 | 5年かつ900日 | ||
| ヘルパー2級以上 | ||||
| 児童指導員任用資格 | ||||
| 保育士 | ||||
| ③国家資格 | 医師・保健師・看護師 | 3年かつ540日かつ国家資格による業務に5年以上従事 | ||
| OT・PT・ST | ||||
| 社会福祉士 | ||||
| 介護福祉士 | ||||
| 精神保健福祉士 | ||||
| あんま・はり・きゅう・柔整師 | ||||
| 視能訓練、義肢装具、歯科衛生士 | ||||
| 栄養士、管理栄養士 | ||||
上記は簡易表となります。
詳しくは、大阪府サービス管理責任者の要件となる実務経験についてを参照してください。
| 仕事内容 | 資格要件 | |
| 生活支援員 | 食事や入浴、排せつ等の介護を行います。外部サービス利用型の場合は不要。 | なし |
| 世話人 | 個別支援計画に基づき、食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切に援助します。 | なし |
指定基準上の人員配置
起床から就寝までの人員配置(日中を除く)(基本報酬)
- 1日の活動終了時刻から翌朝の開始時刻までを基本とする夜間時間帯を設定し、夜間時間帯以外のサービス提供に必要な人員を配置することが必要です。
夜間配置(加算で算定)
人員欠如減算
サービス管理責任者、世話人、生活支援員の人員配置が基準に満たない場合は、基本単位が100分の70の減算対象となります。
注意点

グループホームは、通所型の日中施設でなく、利用者がグルーホームで暮らしています。
ということは、夜間の体制をどうするか、日中をどうするかを考える必要があり、多くの施設では、夜間の従業員配置(夜間支援体制加算を取ることができる場合があります。)を行っています。
よくある質問

Q 住居追加をする場合は、人員配置基準はどうなりますか?
- A 住居追加の場合は、現在のサービス管理責任者が、追加した住居のサービス管理責任者となることが可能です。人員配置については、原則事業所全体が基準数となります。
当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。
申し訳ありませんが、障がい福祉事業の内容等についての無料相談は行っておりません。
〇 有料相談・スポットコンサル希望の方はこちらをご覧ください。
〇 書類点検サービス(模擬実地指導)を希望の方はこちらをご覧ください。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。